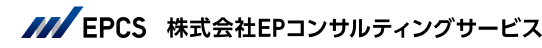コラム
四半期報告書廃止で企業の負担軽減?半期報告書と短信の役割拡大
2024年4月に施行された四半期報告書の廃止から一定期間が経過しました。企業の開示負担軽減を目指し制度が変更された一方で、廃止の影響は今も継続中です。そこで今回は、改めて四半期報告書廃止の背景を振り返り、新たな開示制度の概要や廃止に伴い企業が取り組むべきポイントについて解説します。
四半期報告書廃止の背景と経緯

四半期報告書廃止の背景と経緯に関して3つの視点で解説します。
<四半期報告書廃止の背景と経緯>
・四半期報告書とは
・四半期報告書廃止の理由
・四半期報告書廃止による影響
順番に見ていきましょう。
四半期報告書とは
四半期報告書は、金融商品取引法に基づき上場企業が四半期ごとに作成・提出する法定開示書類です。企業の基本情報や事業内容、財務状況といった投資判断に必要な情報を網羅的に記載しなければなりません。3月決算の企業であれば、6月末、9月末、12月末時点での報告が求められ45日以内に提出する必要がありました。
四半期報告書が導入された目的は、有価証券報告書を補完する役割を果たし、より頻繁な情報開示によって企業の透明性向上を図るためでした。投資家にとっては、企業の最新の経営状況を把握する重要な情報源となっていたものの、企業側には相当な作成負担がのしかかっていたのも事実です。
四半期報告書廃止の理由
四半期報告書が廃止された主な理由は、企業の開示負担軽減と中長期的な企業価値向上の促進です。
上場企業は四半期報告書に加え、決算短信など類似した内容の書類を短期間で作成する必要があり、財務部門の負担が大きくなっていました。頻繁な業績開示が経営者の短期的利益追求を助長し、長期的な投資や戦略立案を阻害するリスクも指摘されていました。さらに、投資家の間でもサステナビリティを重視する動きが強まり、中長期的な企業価値評価の重要性が高まっています。
このような背景から、企業の持続的成長を促す観点で制度の見直しが行われ、四半期報告書の廃止と半期報告書への一本化が決定されました。
四半期報告書廃止による影響
四半期報告書の廃止に伴い、企業の開示負担は大幅に軽減されました。決算短信との重複作業がなくなり、財務部門の業務効率化に寄与しています。
一方で、投資家への情報提供の質を維持するため、四半期決算短信の内容は拡充されています。セグメント情報やキャッシュ・フロー情報といった投資判断に重要な項目が追加されました。
企業は短期的な業績報告にとらわれずに済むため、中長期的な経営戦略の立案や実行に注力できます。投資家は半年ごとの詳細な情報と四半期ごとの要点を組み合わせて、より多角的な企業評価が可能となりました。
新たな開示制度の概要

四半期報告書の廃止に伴い新たに適用された制度は以下のとおりです。
<新たな開示制度>
・半期報告書の役割拡大と提出義務化
・四半期決算短信の義務化と内容充実
・監査法人のレビュー手続きの変更
各内容について概要を解説します。
半期報告書の役割拡大と提出義務化
四半期報告書廃止に伴い、半期報告書の役割が拡大しました。四半期報告書を提出していた上場会社は、新たに半期報告書の提出が義務付けられています。半期報告書の提出期限は、3月決算企業の場合、9月末から45日以内です。
内容面では、従来の四半期報告書に近い詳細な財務情報の開示が求められており、投資家への重要な情報源にもなります。
企業は年2回の詳細な報告書作成に注力できるため、開示負担の軽減と情報の質の向上が期待されます。
四半期決算短信の義務化と内容充実
これまでの四半期決算短信は、取引所規則に基づく開示でしたが、新制度では一律に義務付けられました。従来の決算短信をベースに、投資家からの要望が強いセグメント情報やキャッシュ・フロー情報などが追加されます。四半期ごとの重要な財務情報がスムーズに開示されるようになりました。
将来的には四半期決算短信の任意化も検討されているため、企業の開示姿勢の改善や市場環境の変化を見極めながら、継続的に見直しが行われるでしょう。
四半期決算短信の変更は、企業の適時開示の充実を図りつつ、投資家への迅速な情報提供と企業の開示負担のバランスを取ることを目指しているのです。
監査法人のレビュー手続きの変更
制度変更に伴い、監査法人の四半期レビューの在り方が変更され、第1・第3四半期については任意となりました。ただし、会計不正等が発生した場合には、一定期間のレビューが義務付けられる可能性もあります。半期報告書については、これまでどおり監査法人のレビューが必要です。
企業と監査法人の負担が軽減される一方で、情報の信頼性確保が課題として残ります。取引所による適時開示のエンフォースメント強化や、意図的で悪質な虚偽記載に対する罰則の適用といった対策が講じられています。
今後は、企業の自主的な開示姿勢と外部チェック機能のバランスが重要となるでしょう。
四半期報告書廃止に伴い取り組むべき3つのポイント

四半期報告書廃止に伴い、企業が取り組むべきポイントは以下の3つです。
<企業が取り組むべきポイント>
・四半期決算短信の内容充実
・半期報告書作成体制の整備
・内部統制とリスク管理の見直し
各ポイントについて詳しく解説します。
四半期決算短信の内容充実
四半期報告書の廃止に伴い、四半期決算短信の重要性が増しました。投資家への適切な情報提供を維持するためには、内容の充実が不可欠です。セグメント情報やキャッシュ・フロー計算書など、これまで四半期報告書で開示していた情報を短信に盛り込まなければなりません。経営者による財政状態や経営成績の分析(MD&A)も、詳細に記載するといいでしょう。
単に情報量を増やすだけでなく、重要性の高い情報を簡潔明瞭に伝える必要があります。社内の各部門との連携を強化し、迅速かつ正確な情報収集体制を整えましょう。決算短信の作成プロセスを見直し効率化を図りつつ、質の高い開示が求められています。
半期報告書作成体制の整備
半期報告書提出の義務化に伴い、企業は作成体制を整備しなければなりません。四半期報告書を作成していた企業であっても、半期報告書は新たな作業となるはずです。半期報告書の作成スケジュールを明確にし、関係部署との連携を強化しましょう。財務情報だけでなく非財務情報の収集・分析にも注力し、投資家にとって有用な情報を提供しなければなりません。
監査法人とのコミュニケーションを密にし、レビュー手続きを円滑に進める体制も必要です。半期報告書の作成に携わる担当者のスキルアップも欠かせません。関連する法令や会計基準の理解を深め、質の高い報告書を作成できる人材を育成できれば、長期的な企業価値向上につながります。
内部統制とリスク管理の見直し
四半期報告書の廃止に伴い、企業の内部統制とリスク管理体制の見直しが必要です。四半期レビューが任意化されたため、自社の財務情報の信頼性を担保する仕組みづくりが求められます。四半期ごとの決算プロセスを再検討し、チェック体制を強化しましょう。複数の目で確認する体制や、ITシステムを活用した自動チェック機能などの導入もいいでしょう。
不正リスクの評価と対応策の見直しも必要です。四半期ごとの外部チェックが減るためで、不正のリスクが高まるからです。経営者による財務報告の信頼性に関する評価プロセスを強化し、開示内容の正確性を担保しましょう。
まとめ
四半期報告書の廃止は、企業に開示負担軽減や中長期的な企業価値向上といったメリットをもたらしました。一方で、決算短信の内容充実や半期報告書作成体制の整備、内部統制とリスク管理の見直しといった新たな課題も抱えています。
制度変更に対応した決算を効率よく実施したいのであれば、株式会社EPコンサルティングサービスをご活用ください。高い専門性を持ったプロフェッショナルチームが高品質かつスピーディに決算業務をサポートいたします。