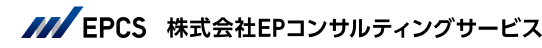コラム
現代にも生きる比較優位の原則
1.比較優位の原則とは
比較優位の原則とは、イギリスのデヴィッド・リカードが1819年の著書「経済学及び課税の原理」の中で唱えた貿易に関する原則です。この考え方は現代でも通用するところがあると思いますので、紹介させていただきます。
比較優位の原則とは、自由貿易の下では、自国が生産している財の中で比較して得意(優位)なものを輸出して、不得意(劣位)なものを輸入したほうが、自国にとって有利な貿易を行うことができるという原則です。この場合の得意なものとは、他国との比較ではなく、自国で生産しているものの中で最も得意なものをいいます。この場合は、絶対的に優位である必要はありません。例えば、自国がリンゴとブドウを生産していると仮定します。ブドウとリンゴどちらの生産も得意であっても、比較してブドウの生産よりリンゴの生産の方が得意であれば、得意なリンゴのみを生産してそれを輸出し、不得意なブドウは輸入するようにします。そうすれば、自国が最も発展する貿易を行うことができます。これが、比較優位の原則です。
2.現代でも生きる比較優位の原則
比較優位の原則は貿易に関する原則ですが、この原則は現代の会社の事業においても該当する原則です。
それぞれの会社はそれぞれの得意分野がありますが、同時に経理を行っている会社も多いと思います。当然ですが、会社はその得意分野において経済活動に貢献していることでしょう。
この場合、比較優位の原則によれば、例えその会社が、経理業務が得意であっても、より得意なそれぞれの専門分野に力を集中して企業活動をしたほうが、会社に有利な状況を生み出すことができることになります。
いかがでしょうか。
一見、当たり前と思えることですが、大変重要なことが1819年にリカードによって紹介されているのです。
3.アウトソーシングの活用
そこで、もし御社の経理に多くの力を投入しているようであれば、その経理部門をアウトソースしてみるというのはいかがでしょうか。私たちEPコンサルティングサービスは、経理の部門におきましては、その分野に得意なスタッフを大勢抱えております。当たり前ではありますが、弊社での最も得意な分野は経理や税務に関する業務です。
御社内で比較して最も得意ではない分野(全く不得意というわけでなく、比較して得意でないという意味です。)と考えられる経理を弊社に行わせていただけば、ここに比較優位の原則が成り立ちます。比較優位の原則が成り立てば、御社はその力を御社の最も得意な分野へ投入することができます。それは御社の発展につながるものと確信いたします。
鈴木 康功Yasunori Suzuki
ACCTソリューション事業部 マネージャー 税理士 税理士法人EOS社員 2003年税理士試験合格。2005年税理士登録。会計事務所を経て、2009年EPCSに入社。