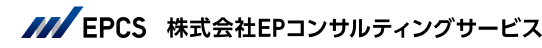コラム
再委託とは?許可するメリットとリスクを解説!契約書の例文も紹介します
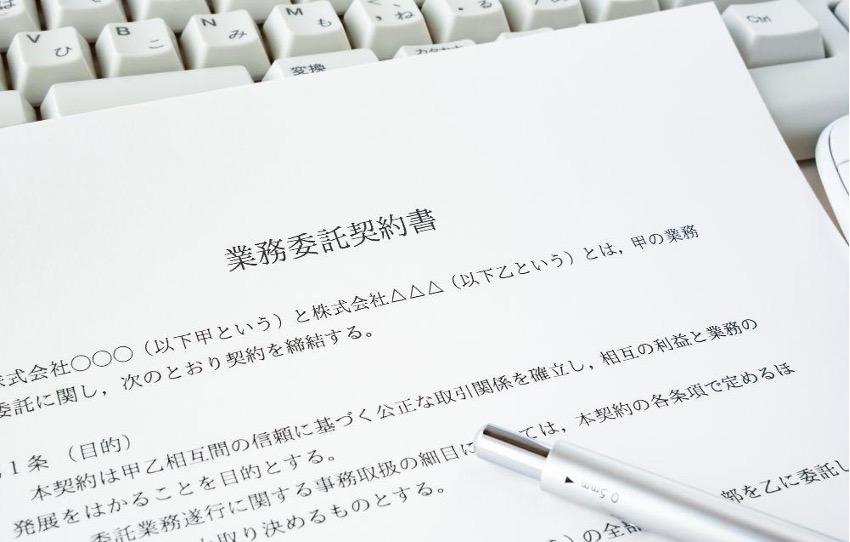
再委託の許可を検討していても、「リスクがあるのでは?」「自社にメリットはある?」など不安・疑問を抱える人もいるでしょう。そこで今回は、再委託を許可するメリット・リスクについて詳しく解説します。
業務委託の契約書に関する例文も紹介しているため、再委託を検討する際は参考にしてください。一通り目を通せば、再委託が自社の状況に合っているか、将来的に再委託を継続させるべきかなどが判断できるでしょう。
再委託とは

再委託とは、委託された業務を第三者に再度委託することを言います。再委託によって、業務効率化や依頼を受けやすいなどのメリットがある一方で、情報漏洩などのリスクを伴います。
本項目では、再委託を行う法律上の問題について解説しますので、トラブルに発展しないためにも目を通してみてください。
再委託は行っても問題ない?
法律上、「請負契約」の場合は再委託しても問題ありません。請負契約とは、仕事を完成させることを目的とした契約であり、誰が完成させても問題ないため第三者へ再委託できます。
一方、委任契約の場合は承諾を得られない限り、原則として再委託が認められていません。なぜなら委任契約は、委託先自身が業務を遂行するという信頼にもとづいて成立するからです。
また、派遣社員へ業務を依頼することは、再委託に該当しません。なぜなら派遣社員の指揮は派遣先の企業が行うもので、派遣元の企業に業務を委託するものではないからです。
再委託を許可する3つのメリット
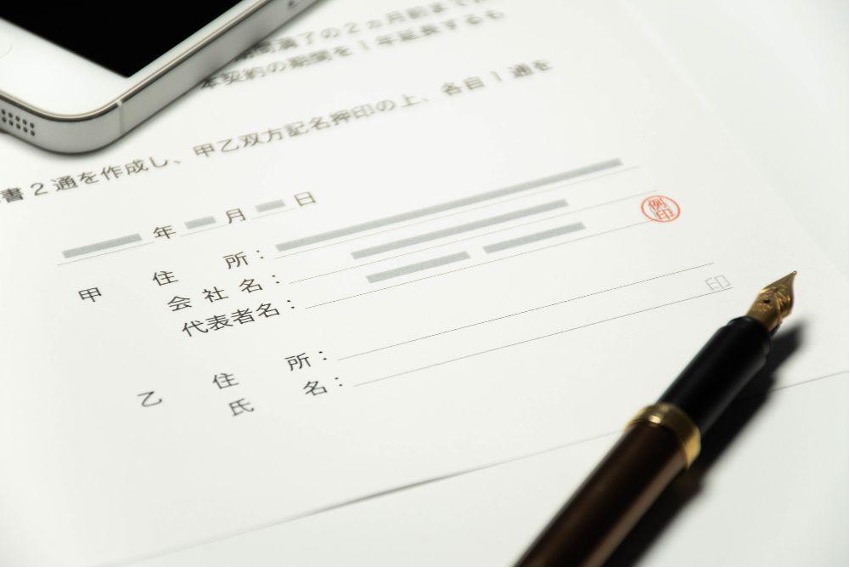
再委託によって得られるメリットは以下の3つです。
<再委託のメリット>
- 製造スピードが上がる
- 成果物の品質が高くなる
- 生産量が多い案件でも依頼しやすい
それぞれのメリットの詳細を解説します。
➀製造スピードが上がる
再委託によって、委託先+再委託先の能力を活用できるため、製造スピードのアップに期待できます。製造スピードが上がる要因は以下のとおりです。
<製造スピードが上がる要因>
- 稼働する人材が増えることで、マンパワーがアップする
- 設備の充実した委託先であれば、業務効率化に期待できる
再委託によってマンパワーや技術力をアップさせられれば、納期が厳しい案件であってもスピーディーな納品に期待できます。
➁成果物の品質が高くなる
再委託は委託先に足りない技術力を補えるため、成果物の品質向上も見込めます。品質向上の主な要因は以下のとおりです。
<品質向上の主な要因>
- 職人や製造・生産設備が補える
- 委託先にないノウハウを活用できる
- 製造・生産ラインを増やすことで、ボリュームのある案件もクオリティを保ちつつ対応してもらえる
委託先では対応できない案件も、再委託によって高品質な納品物を仕上げてもらえる可能性があります。
➂生産量が多い案件でも依頼しやすい
再委託を活用できれば、委託先だけでは対応しきれない生産量の多い案件も依頼しやすくなります。また再委託では、委託先にない技術・設備・人員を投入できるメリットもあります。
膨大な生産量を1社で受注できる企業は多くありません。そのため再委託を許可することで、依頼する案件の選択肢を増やすこともできます。
さらに、海外の工場へ再委託すれば、コストを抑えつつ生産量の多い案件を依頼できる可能性もあります。コスト削減や生産量アップを目指す場合は、再委託の許可も検討しましょう。
再委託を許可する2つのリスク

再委託には以下の2つのリスクもあります。
<再委託のリスク>
- 情報漏洩のリスクが高まる
- 進行状況が把握しづらくなる
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
➀情報漏洩のリスクが高まる
再委託により機密情報や顧客情報を握る企業が増えることで、情報漏洩のリスクは高まります。再委託は、「関係する人間が増える=情報漏洩の起点が増える」というリスクに向き合う必要があります。
対策の例を挙げていくので、再委託する際の参考にしてください。
<情報漏洩リスクの対策方法>
- 専門部署を作り、委託先のリスク評価を行う
- 定期的に委託先の状況を把握する
- セキュリティ意識向上の教育を行う
- セキュリティ上の要求を含めた契約を行う
情報漏洩リスクを防ぐ上で特に重要なのは、セキュリティ意識の向上と状況把握です。すべて委託先に任せてしまっては、セキュリティ管理の状況がつかめません。そのため事前に従業員向けの教育資料を作成し、緊密に連絡を取り合う環境を構築しましょう。
また、トラブルが発生したときに備えて、セキュリティの要求事項などの契約内容を見直すことも大切です。
➁進行状況が把握しづらくなる
再委託により関連企業が増えると、各業務の進行状況が把握しづらくなり、管理しきれなくなる恐れがあります。委託先が増えれば増えるほど、自社と各委託先の距離は離れていきます。
進行状況をコントロールできなければ、製品のクオリティや業務効率などにも影響を及ぼしかねません。以下の例を参考に、進行状況の把握に取り組みましょう。
<管理方法の具体例>
- 再委託先までの階層を把握する
- フォローアップ体制を構築する
- 委託先へ直接赴く
進行状況の把握には、管理体制の構築が重要です。再委託先までの階層を把握し、定期的に報告が入る体制を整えましょう。
また、定期報告で把握できない要素があれば、直接訪問して状況を確認するというのもひとつの手段です。
再委託については契約書で定めておくと良い
再委託の可否は契約書に定め、起こりうるトラブルを未然に防ぎましょう。再委託の「禁止・許可」それぞれのパターンにおいて、契約書に盛り込むべき文言を解説します。
再委託禁止とする場合
再委託を禁止とする場合、契約書には以下のような文言を盛り込みます。
<再委託禁止の契約書の例>
- 受注者は本事業のすべてを自ら実施するものとする
- 業務のすべてを第三者に委託させてはならない
再委託の禁止については、「再委託禁止事項」として条項を設けておきます。内容を明確に記載し、お互いの認識を統一させましょう。
再委託の条件を盛り込む場合
再委託の条件を盛り込む場合は、以下の文言を契約書内に明示しましょう。
<再委託の条件を盛り込む契約書の例>
- 双方協議の上、委託者が再委託を許可した場合に限り、受託者は再委託をできるものとする
- あらかじめ再委託先の住所、氏名、業務範囲について記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない
再委託の条件を盛り込む際は、勝手に委託契約を結ばれないよう事前の報告義務を課しておくことがポイントです。自社で精査し、セキュリティや業務品質などがチェックできる契約書を作成しましょう。
まとめ
再委託は、製造スピードアップや品質向上などが見込める魅力的な手法です。しかし、情報漏洩や進捗状況の管理が難しいなどのリスクもあるため、許可すべきかどうかは慎重に判断しなければなりません。
また、再委託以外の選択肢を検討する事業者様は、「株式会社EPコンサルティングサービス」へご相談ください。弊社では、経理・会計や税務、給与計算などの業務を専門性の高いプロフェッショナルチームがサポートいたします。依頼内容に応じてさまざまなサービスを提供しますので、お気軽にご相談ください。