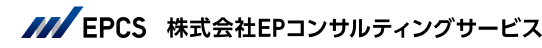コラム
労働契約関係における権利と義務
「ブラック企業」「ホワイト企業」「モンスター社員」「シュガー社員」「社畜」。
一昔前では、耳にするようなことが無かったこれらの言葉が、今は何ら違和感なく、多くの方が日常で使っているのではないでしょうか。また、最近では、職場が緩すぎて(甘すぎて)、成長できないから転職をする人がいるようなこともインターネット等のメディアを通じて見ることもありますし、14日前に退職を申し出れば、もう会社に行かず、そのまま辞めても大丈夫、なんてことも耳にします。
このような言葉を見聞きすると、「労働関係における権利と義務」ということを、自分の中で、ふと考えることがあります。
そこで今回は、権利と義務という視点で、会社と労働者がそれぞれ持つ権利、そして行わなければいけない義務をいくつか見て行きたいと思います。
そもそも、なぜ?
なぜ、今回「権利と義務」というテーマに至ったのか、というところですが、上記に記載した通り、メディアの記事や様々な企業の人事の方のお話を聞く中で、「そもそも、やるべきことを、しっかり出来ているのかな?」と思うことが、以前よりも増えて来たように感じたことがきっかけです。
例えば、職場が緩すぎて(甘すぎて)、成長できないから転職をするというケースを取っても、その従業員がやるべき業務を会社はやらせているのか、従業員は出来ているのか、ということなり、必ずしもパフォーマンスが良くなく出来ていないのであれば、そのことは伝えているのか、又はパフォーマンスを上げるための措置は取っているのか、ということになります。
もし、パワハラと言われたくないから指導をしたくない、何も言われないから自分は良く出来ていると思っていると言うことになりますと、結果的に、成長できないから辞めるという、誰も得をしない結末が待ち受けているのではと思います。
基本的な権利義務
労働契約を締結することにより、労働者は会社で働き、その労働に対し、会社は賃金を支払うこととなります。この働いた結果に対し、賃金が支払われるという流れは誰も疑うことのないものかと思いますが、この労働契約を締結したことにより発生する権利義務関係を会社と労働者の視点で見てみると次のようになります。
【会社】
- (権利)指揮命令権
- (義務)賃金支払い義務
【労働者】
- (義務)労務提供義務
- (権利)賃金請求権
会社側の目線としては、労働者を労働契約に基づき働かせる(指揮命令権を行使する)代わりに賃金を支払う(賃金支払義務が生じる)こととなり、労働者の目線としては、労働契約に基づき労働する(労務提供義務を果たす)代わりに賃金を得る(賃金請求権を得る)こととなります。
この会社と労働者がそれぞれ持つ権利義務は、労働契約を締結することにより発生する最も基本的な権利義務関係となります。
なお、念のための追記となりますが、会社が労働者を働かせる(指揮命令権を行使する)のに、どんな働かせ方をしても良いというわけではなく、労働基準法等で定められた一定の基準の中で働かせる(指揮命令権を行使する)こととなりますし、労働者も労働契約で定められた労務を提供出来ないのであれば、賃金の全額を得ることは出来ないこととなります(欠勤や遅刻及び早退がイメージし易いかと思います。)。
付随的権利義務
上記の働かせる/働く、賃金を支払う/得る、という基本的権利義務関係の他にも、労働契約を締結することにより発生する権利義務がいくつかあります。 ここでは、企業が労働者に対し、また、労働者が企業に対し負う義務について、主要なものをいくつか見て行きたいと思います。
<企業が労働者に対して負う義務>
①安全配慮義務
安全配慮義務とは、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとなります(労働契約法5条)。
②職場環境配慮義務
職場環境配慮義務は安全配慮義務に含まれるものと考えられていますが、近時の分かりやすい例ですと、各種ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ等)が起きない環境を保つよう配慮するものとなります。
<労働者が企業に対して負う義務>
①誠実労働義務
誠実労働義務とは、労働者の行う労務の提供は労働契約で定められた債務の本旨に従ったものではなくてはならない、というものです。例えば、外勤営業であるにも関わらず、外勤を拒否し内勤をしていた場合や、合理的な理由があり就業規則等で身だしなみや服装を制限しているにも関わらず、それに従わない場合には、この義務に違反することとなります。
②企業秩序維持義務
企業秩序維持義務を簡単に言いますと、会社で働くにあたり企業秩序を維持するために服務規律等を守る義務が労働者にはあるということになります。そのため、使用者は企業秩序を維持するために、企業の円滑な運営に支障が来す恐れがある行為を規制の対象とし、労働者に懲戒を課することも可能とされています。
これからの労務管理に向けて
以上、労働契約関係における権利と義務ということで、基本的な権利義務関係、そして付随的な権利義務関係について、触れさせて頂きました。日々の業務を実施して行く中で、自らの権利を意識することはあっても、その裏側にある義務をしっかりと果たせているのかという視点は、なかなか持ちづらいものではないかと思いますので、今回のコラムがそのきっかけになれば幸いです。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、日々変化する労働環境に対し、給与計算、社会保険手続き、そして労務相談をワンストップで提供することにより、企業及び人事担当者が抱える問題及び課題をサポートしておりますので、気になることがありましたら、お気軽にお声がけ頂きたいと思います。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。