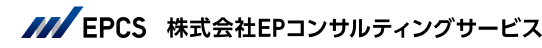コラム
減損会計とは?対象となる固定資産や手順を解説します
減損会計とは、財務諸表に企業の実態を正確に反映するために重要な会計処理です。しかしあまり知られていないため、減損会計の対象や方法などを把握しておかないと、いざという時に困ってしまうかもしれません。そこで本記事では、減損会計の概要や対象となる資産、手順についてわかりやすく解説します。
減損会計とは

減損会計とは、資産に投資した際に収益が出ないことがわかった時点で、回収が期待できる金額まで減額する会計処理を指します。具体的には、資産の下落分を帳簿価格から差し引くと同時に、損益計算書上で特別損失として減損損失を計上する方法が一般的です。
たとえば、200万円の投資回収額が見込めると考えて100万円の機械を購入した場合、80万円の収益しか出ない結果がわかったとしましょう。そのとき資産価値を80万円に記載し直すとともに、差額の120万円を減損損失として計上することが減損会計に該当します。
なお、減損会計は上場企業や大規模な会社には義務付けられていますが、中小企業は対象外です。
減損会計の目的
減損会計の目的は、企業の財務諸表の正確性と信頼性を高める点です。財務諸表に企業の実態を正確に反映するには、資産の適切な価値評価と減損の認識が欠かせません。
また減損会計は、企業の投資に対する資産効率を向上させる効果も期待できます。投資家や債権者に対して企業の経済状況を適切に評価してもらうためにも、減損が認識される企業は減損会計を行うべきでしょう。
減損会計の対象になる固定資産

減損会計の対象になる固定資産は、主に以下の3つです。
<減損会計の対象になる固定資産>
①有形固定資産
②無形固定資産
③投資その他の資産
それぞれどのような資産を指すのかわかりやすく解説します。
①有形固定資産
有形固定資産とは、以下のような資産が挙げられます。
<有形固定資産の例>
- 土地
- 建物
- 車両
- 機械装置
- 工具器具
通常、有形固定資産は減価償却によって価値を徐々に減少させるのが一般的です。しかし、事業がうまくいかず、売上が思うように確保できない見込みであるといった場合に減損会計を行うケースがあります。
②無形固定資産
無形固定資産には、以下のような資産が挙げられます。
<無形固定資産の例>
- 特許
- 商標
- 営業権
- ブランド価値
- ソフトウェア
無形固定資産とは、物理的な形を持たない特許やソフトウェアなどの資産です。通常、無形固定資産の価値も資産取得時の費用を元に、減価償却によって徐々に減少させられます。しかし、有形固定資産と同様に期待通りの利益が得られなくなったなどの場合には、減損会計を行うケースがあります。
③投資その他の資産
投資やその他の資産も、一般的には減損会計の対象です。
<投資その他の資産の例>
- 長期貸付金
- 投資用不動産
- 関連会社への出資
投資その他の資産には、株式や債券の保有、関連会社への出資などが含まれます。購入した株式の株価が著しく下落し、回復の見込みがないと判断できるといった場合には、減損会計を行うケースがあります。
【例外】減損会計の対象にならない固定資産
固定資産には、減損会計の対象にならないものもあるため注意が必要です。減損会計の対象外となる固定資産の代表例は以下のとおりです。
<減損会計の対象にならない固定資産の例>
- 金融商品にかかる会計基準に規定される金融資産
- 税効果会計にかかる会計基準にもとづく繰延税金資産
- 退職給付にかかる会計基準にもとづく前払年金費用
- 研究開発費等にかかる会計基準にもとづいて、固定資産として計上される市場販売目的のソフトウェア
個別の減損会計に関する指針が定められている一部の金融資産・繰延税金資産なども対象外とされています。また仕入れた商品などの価値が著しく下落した場合も、減損会計ではなく、評価損として計上します。
減損会計の手順

減損会計では、まず減損損失をすべきかどうか「判定」してから、実際の減損損失の金額を「測定」するのが一般的です。手順を以下の4ステップに分けて詳しく解説します。
<減損会計の手順>
①資産をグループ分けする
②減損の兆候があるか判定する
③減損損失の有無を確認する
④減損損失を測定して計上する
①資産をグループ分けする
最初に固定資産を特定の単位やカテゴリにまとめる作業である「資産のグルーピング」を行います。減損会計では投資額に見合った金額を回収しているかどうかを資産のグループごとに判定するため、資産のグルーピングでまとめれば減損損失の計算を効率的に行えます。
資産のグルーピング方法は、会計基準や企業の内部方針によって異なる場合があります。適切なグルーピング基準を設定し、会計基準や規制に準拠しながら減損会計の手続きを実施しましょう。
②減損の兆候があるか判定する
資産のグルーピングでまとめた資産グループごとに、減損の兆候があるかどうか判定します。具体的には、事業を行う固定資産に減損が生じている可能性について判断する必要があるのです。減損の兆候の判定には、以下のような要素が考慮されます。
<減損の兆候の判定方法>
- 企業の外部要因の変化:需要の低下、競争の激化、法的な変更、技術の進歩
- 企業の内部要因の変化:事業の不振、資産の老朽化、生産性の低下、技術の陳腐化
- 資産の価値への影響:市場価格の変動、キャッシュフローの見通し、同業他社との比較、将来の利益の見込み
- 過去の実績:資産の収益性や価値の変動、キャッシュフローの安定性
減損の兆候となりうる要素を総合的に評価し、減損の兆候について判断します。減損の兆候を見つけた場合には、減損の有無を確認した上で早期の対応が重要です。
③減損損失の有無を確認する
減損の兆候が見られた場合には、対象の資産グループで実際に減損会計を行う必要があるかを判定する必要があります。減損会計が必要かどうかは、対象の資産グループの帳簿価額と「割引前将来キャッシュフロー」との総額を比較によって判断が可能です。
割引前将来キャッシュフローとは、対象資産を使い続けて生み出されるキャッシュフローについて、時間価値を加味せずすべて合計したものを指します。減損会計を実施するかどうかは、以下のように割引前将来キャッシュフローが帳簿価額を上回っているかどうかで決まります。たとえば、帳簿価額が700万円の固定資産が年間50万円のキャッシュフローを10年間生み出すと仮定しましょう。
<帳簿価額と割引前将来キャッシュフロー額>
- 帳簿価額:700万円
- 割引前将来キャッシュフローの総額:500万円(50万円×10年)
割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価格を下回っているケースでは、減損損失が認識できると判断できます。逆に、割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を上回っている場合は、減損が発生しないため減損会計を行う必要はありません。
つまり、減損損失の有無を判定する際は割引前将来キャッシュフローの総額を算出して、帳簿価額と比較して行うのです。
④減損損失を測定して計上する
財務諸表に計上するために、減損があると判定された資産グループの減損損失の金額を測定します。減損損失の測定方法は、以下のとおりです。
<減損損失の測定方法>
- 帳簿価額−回収可能価額=減損損失
回収可能価額とは、対象の固定資産を使用して将来的に回収できるキャッシュフローの総額です。回収可能価額は「使用価値」と「正味売却価額」を計算し、いずれか金額が高いほうを採用するのが一般的です。
使用価値とは、対象の固定資産を使用し続けて得られる総額であり、一方正味売却価額とは、減損損失の認識時点の価格から処分費用を差し引いた金額を指します。
回収可能額が確定して減損損失が測定できたら、損益計算書の特別損失に計上しましょう。また、減損会計処理を資産の帳簿価額に反映するために、財務諸表で資産の価値を修正する必要もあります。
まとめ
本記事では、減損会計の特徴や対象となる資産、実際に処理する際の手順を解説しました。減損会計は企業の財務諸表の正確性と信頼性の向上や、投資家や債権者に対して企業の経済状況を適切に評価してもらうために重要な会計処理です。
有形固定資産や無形固定資産、投資などの多くの資産が対象とされている一方、一部の金融資産や繰延税金資産が対象から外れている点に注意しなければなりません。また減損会計の手順もやや複雑であるため、資産のグルーピングや減損の兆候の判定や測定などに詳しくない場合は負担が大きくなる可能性もあります。
減損会計の処理が難しいと感じたならば、「株式会社EPコンサルティングサービス」のご利用をぜひ検討してください。株式会社EPコンサルティングサービスが提供するプロフェッショナルアウトソーシングサービスでは、減損会計などの会計業務に高い専門性を持ったチームが、高品質かつスピーディに幅広く対応いたします。
当然他の会計処理にも深く精通していますので、減損会計などの処理でお困りの場合には、株式会社EPコンサルティングサービスにお任せください!