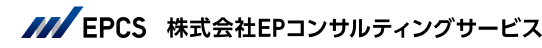コラム
年末調整で会社のミスが発覚!過年度分の修正方法と再発防止策
毎年、会社が行うべき作業のひとつに年末調整があります。決まったルールに従い作業を行っても、時にはミスが発生する場合もあるでしょう。安心して従業員に働いてもらうには、ミスのない年末調整が求められます。
本記事では、年末調整でよくある会社のミスや修正方法、再発防止策について解説します。ミスの発覚や、税務署からの修正通知が届き、お困りの担当者は最後までご覧ください。
年末調整でよくある会社のミス

年末調整でよくある会社のミスは、主に以下の3つです。
<年末調整でよくある会社のミス>
・扶養関連のミス
・控除証明書の確認不足
・年末調整の改正内容の適用ミス
順番に確認していきましょう。
扶養関連のミス
年末調整でよくある会社のミスで多いのが扶養関連のミスです。特に、扶養家族の人数変更や配偶者の収入に関する誤りが多く見られます。例えば、年内の結婚や出産、離婚により扶養状況が変化したにもかかわらず、適切に反映されていないケースがあります。
扶養関連のミスは従業員の税金額に直接影響を与えかねません。扶養関連の情報を正確に把握して、12月31日時点の状況を適切に反映しましょう。
控除証明書の確認不足
控除証明書の確認不足もよくある会社のミスです。生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除には、適切な証明書が必要です。従業員が控除証明書を紛失したり、提出を忘れたりするケースが後を絶ちません。
また、会社側が提出された証明書の内容を十分に確認せず、控除額を誤って計算してしまうミスも生じます。従業員の税金還付額に影響を与えたり、後日の修正作業が生じたりするので注意しましょう。
年末調整の改正内容の適用ミス
税制改正により、年末調整の制度は毎年のように変更されます。年末調整を適切に行うには、改正内容を正確に理解して正しく適用しなければなりません。例えば、令和3年分の改正では、年末調整書類の押印義務がなくなるといった変更もありました。令和2年分では給与所得控除の引き下げや基礎控除の見直しなど変更が行われています。
改正内容を正しく反映せずに年末調整を行うと、後日の修正につながりかねないため注意しましょう。
会社のミスが発覚した場合の年末調整の修正期限
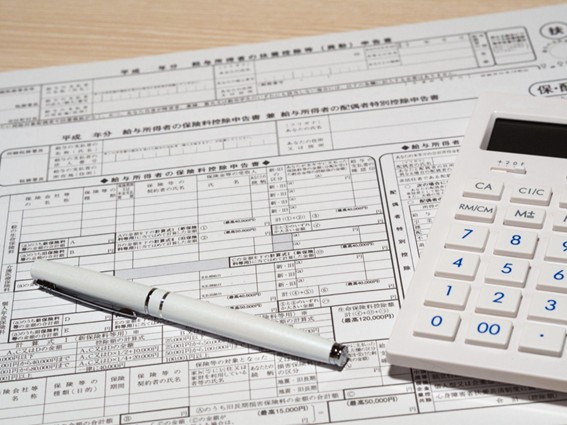
会社のミスが発覚した場合、年末調整が修正できる期限は決まっています。本稿では、修正可能な期限と、万が一、期限を過ぎてしまった場合の対応について詳しく解説します。
修正可能な期限
万が一、年末調整のミスが見つかったら、すぐに修正対応を行いましょう。修正ができるのは、源泉徴収票を従業員に交付する前かつ、 法定調書の提出期限である翌年1月31日 までです。期間内であれば、比較的スムーズに修正作業を進められます。
12月に実施した年末調整で1月中旬にミスが発覚した場合、修正期限までにはまだ余裕があります。給与システムの修正や従業員への説明といった実務的な作業が伴う場合は、注意が必要です。修正内容によっては源泉徴収票の再発行も必要になる場合もあります。
できるだけ早く修正に着手し、期限内に完了させなければなりません。期限内の修正は、従業員との信頼関係を維持し、税務署とのトラブルを避けるためにも不可欠です。
期限後の対応
1月31日の期限を過ぎてしまった場合は、別の方法で対応しなければなりません。税務署に連絡を入れて状況を説明し、指示に従いましょう。修正手続き自体は複雑になってしまいます。担当者だけで処理をせず、顧問税理士といった専門家へ相談するのがおすすめです。
期限後の修正では、源泉所得税の過不足調整が必要になります。不足の場合は追加納付、過剰の場合は還付請求を行います。延滞税が発生する可能性もあるため注意が必要です。
また、従業員への説明も重要です。特に、追加の税金納付が必要な場合は、丁寧な説明と対応が求められます。会社の信用にも関わる問題なので、誠実な対応を心がけましょう。
税務署から過年度分の修正通知が来たら
税務署から過年度分の年末調整の修正通知が届いた場合、迅速かつ適切に対応しなければなりません。修正通知は年末調整の半年後、多くの場合8月以降に届きます。
通知を受け取ったら、まず内容を確認し、該当する従業員の状況を把握しましょう。従業員にヒアリングを行い、申告内容の修正と再計算を速やかに行います。多くの場合、追加徴収が必要となるため、不足分の税金を納付しなければなりません。
配偶者控除や扶養控除、基礎控除などに誤りが見つかる場合が多いです。修正作業は企業の責任で行う必要があり、従業員の確定申告では対応できません。適切な対応は、従業員との信頼関係維持や法令遵守の観点から非常に重要です。
年末調整でミスを防ぐには

年末調整でミスが生ずると、修正や手続きなど多くの工数がかかってしまいます。ミスを防止するには、以下の3つの対応策を活用するといいでしょう。
・書類提出を早める
・複数人でチェックを行う
・外部の専門サービスを利用する
それぞれについて詳しく見ていきます。
書類提出を早める
年末調整のミスを防ぐには、書類提出の期限を早めるといいでしょう。12月に入ってから書類を集める会社も見られますが、確認する時間が不足してしまいます。10月頃から従業員に書類の準備を呼びかけ、11月中旬までに提出してもらうのが理想的です。
早めに提出してもらうには、社内メールやポスターで積極的に周知します。提出が遅れがちな従業員が確定しているのであれば、個別に声をかけるのも有効です。
早期提出を進めれば、余裕を持った書類準備ができるため、記入ミスの削減につながります。会社側も十分な確認時間が確保できるため、ミスが発覚しても余裕を持って修正可能です。年末の繁忙期を避けて、正確な年末調整が実施できます。
複数人でチェックを行う
オーソドックスな手法であるものの、複数人によるチェックは非常に有効です。一人で確認すると、見落としや思い込みによるミスが起こりやすくなります。経理担当者が入力した内容を、別の担当者によってダブルチェックを行う仕組み作りが重要です。
チェックリストを作成し、確認項目を明確にすれば漏れのない確認につながります。特に注意が必要なのは、扶養控除や保険料控除などの複雑な計算が必要な項目です。電卓を使って確認するなど、入念なチェックが求められます。
複数人でのチェックは時間がかかるものの、修正作業にかかる時間と労力を考えれば、十分に価値がある取り組みです。従業員の信頼を守り、正確な年末調整を実現するためにもチェックの体制づくりは欠かせません。
外部の専門サービスを利用する
年末調整の複雑さや頻繁な制度変更に対応するには、外部の専門サービスを利用するのもおすすめです。税理士事務所や社会保険労務士事務所 などの専門家に依頼すれば、最新の税制に沿った正確な処理が可能となります。専門家は豊富な経験と知識を持っているため、複雑なケースにも適切に対応可能です。
クラウド型の年末調整サービスを利用するのも有効です。自動計算機能も充実しているため、人為的なミスを削減できます。従業員自身がスマートフォンやPCから必要事項を入力できるシステムもあるため、書類の紛失や記入ミスのリスク軽減につながります。
外部サービスの利用にはコストがかかるものの、ミスによる修正作業や従業員の信頼低下を考えれば、十分に価値のある投資といえるでしょう。
まとめ
年末調整のミスは、扶養関連や控除証明書の確認不足、改正内容の適用ミスといった要因で発生します。ミスを防止するためには、書類提出の早期化、複数人でのチェック体制の構築、外部の専門サービスの利用といった対策が必要です。
効率よく年末調整を実施したいのであれば、株式会社EPコンサルティングサービスをご活用ください。お客様のニーズに合わせた案内・記入例などの資料をご用意して、内容チェックから問い合わせ対応まで行き届いたサービスを提供します。