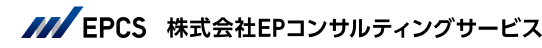コラム
法人税計算の基礎知識│計算方法を3つのステップで徹底解説&注意すべき点も紹介

法人税の計算は多くの経営者や経理担当者にとって頭を悩ませる業務のひとつです。複雑な計算方法や頻繁に変わる税制に対応するのは容易ではありません。それでも、正確な法人税計算は企業の財務健全性を保つためには不可欠です。
そこで今回は、法人税計算の基礎知識から具体的な計算方法まで、3つのステップで分かりやすく解説します。計算時に注意すべきポイントも紹介しますので最後までご覧ください。
法人税計算の基礎知識

まずは法人税計算の基礎について、以下の3つの視点で説明します。
<法人税計算の基礎知識>
・法人税の定義
・法人税の種類
・法人税が課税される法人と課税されない法人
順番に見ていきましょう。
法人税の定義
法人税とは、法人が事業活動によって得た所得に対して課税される国税です。法人の所得金額は「益金の額」から「損金の額」を差し引いて計算されます。
ここで注意すべきなのは、企業会計上の利益がそのまま課税対象になるわけではないという点です。法人税法に基づいた調整が必要となります。例えば、交際費や寄付金などは、損金算入に一定の制限があるため注意しなければなりません。
法人税は自主申告制度を採用しており、法人自らが計算して申告・納付します。申告期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内と定められています。期限を過ぎると延滞税がかかるだけでなく、青色申告法人が2期連続で期限後申告をすると、青色申告の承認が取り消されることもあるので注意が必要です。
法人税の種類
法人に課される税金は法人税だけではありません。法人が負担する主な税金として、国税である法人税のほかに、地方税である法人住民税と法人事業税があります。これらを総称して「法人税等」と呼ぶことが一般的です。
法人住民税は、法人が事業を行う地域の自治体に納める税金で、都道府県民税と市町村民税に分かれます。法人住民税には、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金や従業員数に応じて課税される「均等割」があります。
法人事業税は、法人の事業活動に対して課税される地方税で、公共サービスを利用したことに対する負担という性格を持っています。赤字の場合は免除されることもあるものの、資本金が1億円を超える場合は免除されません。
法人税が課税される法人と課税されない法人
法人税が課税される法人は、主に「普通法人」と「協同組合等」の2種類です。普通法人には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、医療法人などが含まれ、すべての所得に対して法人税が課税されます。協同組合等には、生活協同組合、農業協同組合、信用金庫などが含まれ、普通法人と同様に課税されますが軽減税率が適用されます。
一方、法人税が課税されない法人としては、「公共法人」「公益法人等」「人格のない社団等」の3種類です。なかでも公共法人(地方公共団体、日本政策金融公庫、国立大学法人など)は完全に非課税です。
公益法人等(一般社団法人、NPO法人、学校法人など)と人格のない社団等(PTA、マンション管理組合など)は原則として非課税ですが、収益事業から生じた所得に限り課税対象となります。
法人税計算の方法を3つのステップで解説

ここからは法人税計算の方法を以下の3つのステップで解説します。
<法人税計算の方法>
・所得金額の計算
・法人税額の計算
・税額控除の適用
ステップごとに見ていきましょう。
所得金額の計算
法人税計算の最初のステップは所得金額の計算です。所得金額は「益金の額」から「損金の額」を差し引いて算出します。
益金とは収益に相当するもので、売上高や受取利息、雑収入などが対象です。一方、損金は費用に相当するもので、仕入原価、給与、地代家賃などの経費が該当します。ただし、企業会計上の収益や費用がそのまま益金や損金になるわけではありません。
例えば、交際費は一部しか損金算入できませんし、受取配当金は一定割合が益金不算入となります。また、減価償却費や引当金、繰延資産などについても税法上の規定に従って調整する必要があります。
これらの調整を行った上で、最終的な課税所得を算出します。この所得金額が法人税の課税標準となるため、正確な計算が求められます。
法人税額の計算
所得金額が算出されれば、次のステップは法人税額の計算です。法人税額は、所得金額に税率を乗じて算出します。
2025年現在、普通法人の基本税率は23.2%です。中小法人(資本金1億円以下)には、年800万円以下の所得部分に対して15%の軽減税率が適用されます。また、公益法人等や協同組合等には、それぞれ異なる税率が適用されます。
事業年度が1年未満の場合は、所得金額を1年分に換算した金額に税率を乗じ、その結果に事業年度の月数を12で割った数を乗じた額が税額です。このように、法人の種類や規模、事業年度の長さによって計算方法が異なるため、自社の状況を正確に把握しなければなりません。
税額控除の適用
法人税額を算出した後、税額控除を適用します。税額控除とは、算出された法人税額から一定の金額を差し引く制度で、企業の特定の活動を促進するために設けられています。主な税額控除には、賃上げ促進税制や投資促進税制などがあります。
これらの税額控除は、適用要件を満たし、適切な書類を添付して申告することで初めて受けられるものです。税額控除を最大限に活用すれば、企業の税負担を合法的に軽減できるため、適用可能な制度を事前に把握しておかなければなりません。
法人税計算で注意すべき点
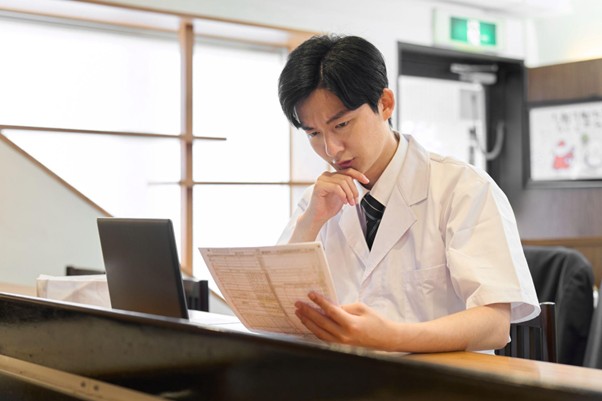
最後に法人税計算で注意すべき3つの点について解説します。
<法人税計算で注意すべき点>
・前期との相違点を確認する
・中間納付額の入力誤りに注意する
・ダブルチェックを行う
順番に見ていきましょう。
前期との相違点を確認する
前期との相違点の確認は法人税計算において不可欠です。税法改正や事業内容の変化によって、適用される税法や計算方法が変わることもあるため、前期と同じように処理してしまうと、誤った税額を申告してしまう可能性があるからです。
税制改正情報の確認はもちろん、固定資産の取得や売却、新たな事業の開始など前期と異なる点がないかを洗い出しましょう。前期の申告書や計算書類と照らし合わせ、勘定科目の増減や金額の変動などの把握も有効です。前期との違いを正しく理解し、正確な法人税申告を行いましょう。
中間納付額の入力誤りに注意する
法人税計算における中間納付額の入力は慎重に行わなければなりません。入力ミスがあると、過大に税金を納めてしまったり、逆に不足による延滞税が発生したりする可能性があるからです。
中間納付時に発行された領収書や納付書を必ず確認し、記載されている金額を正確に入力しましょう。金額の桁数や小数点以下の処理には注意が必要です。入力ミスに気づいたら、速やかに税務署に連絡し修正手続きを行ってください。
ダブルチェックを行う
法人税の計算後にはダブルチェックを習慣化しましょう。法人税計算は複雑で金額も大きく、どうしても計算ミスや入力ミスが発生しやすいからです。ダブルチェックでミスを早期に発見できれば、早期に修正対応できます。
計算を担当した者とは別の担当者が、使用した資料や根拠となる法令などを参照し、もう一度最初から計算の流れを確認します。税率の適用や損金算入の可否など、判断が難しい箇所は念入りにチェックしましょう。税務ソフトのチェック機能や税理士への相談も有効です。
まとめ
法人税計算は企業の財務健全性を保つために非常に重要な業務です。正しく計算を行い申告を行わなければ、必要以上の税負担になるだけでなく企業の信用も失いかねません。本記事で解説した法人税計算の基礎知識から具体的な計算方法、注意点を参考に適切な申告を行いましょう。
効率よく適切な法人税計算を行いたいのであれば、EPコンサルティングサービス(EPCS)の経理・会計・税務アウトソーシングをご活用ください。高い専門性を持ったプロフェッショナルチームが、高品質かつスピーディーにサービスを提供いたします。