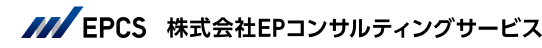コラム
「労働者」とは
2022年度もついに終了を迎えようとしています。
皆さん自身として、又は所属している組織やその一員として、この1年間はいかがでしたでしょうか。この一年も、多くの方と接する機会を頂きましたが、労働環境の変化、働き方への意識や要望等、個人そして企業が求めるもの/求められるものが、今までに感じることのないスピードで変化し続けているのではないかと感じています。そのような中で特に、フリーランス、兼業/副業、独立、そのような言葉やこれらに関するご相談を非常に多く聞いた1年だったと思っております。
そこで今回は、従来は当たり前であった「労働者」として働くことについて、そもそも「労働者」とはという視点で見て行きたいと思います。
そもそも「労働者」とは…
「労働者」と言った時、そもそも、どのような人をイメージするでしょうか。
単純に働いている人、と言ってしまえば大きく外れることはありませんが、そうなると、会社員、プロ野球選手、大相撲の力士、フリーの配達員等、全ての人が労働者に該当することになります。もちろん、これも間違いではないと思いますが、多くの場合、労働者とは労働基準法の保護を受けることが出来る人を指しています。
そして、労働基準法第9条では、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定しております。ここでのポイントは、2つ。1つ目は、使用される、そして2つ目は賃金を支払われる、です。
会社に使用され労働し、その労働の対価として賃金を支払われる、この一連の流れに該当する人が労働基準法上の労働者に該当し、労働基準法の保護を受けることが可能となります。
法律いろいろ、労働者もいろいろ。。。
先程、「労働基準法上の労働者」について、簡単に説明させて頂きましたが、「労働者」と一概に行っても、当然、法律が違えば労働者の定義も、当然違ってきます。そぅ、法律いろいろ、労働者もいろいろです。折角の機会ですので、「労働者」という言葉を使っている法律において、それぞれ、労働者がどのように定義されているか見てみましょう。
①労働組合法
労働組合法では、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。」と規定しています(3条)。先程の労働基準法と比較すると「使用される」という文言がないことが、大きなポイントとなります。
②労働契約法
労働契約法では、「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」と規定しています(2条①項)。条文の内容としては、労働基準法に似たものとなっておりますが、労働契約法の場合、請負や委任等であっても、実態として使用従属関係が認められる場合には同法の労働者に該当するものとされております。
③労働者災害補償保険法
次に労働者災害補償法です。皆さんがご存じの通り、仕事中又は通勤の途中に怪我をした場合に国に補償してもらうことが出来ることを定めた法律ですが、法律の名前にも「労働者」という言葉を使い、更に条文上も「労働者」という言葉を使用しているにも関わらず「労働者」の定義はどこにも置かれていません。では、「労働者災害補償保険法における労働者は誰?」と言うことになるのですが、これは「労働基準法に規定される労働者」とされております。これは、1947(昭和22)年に労働基準法と労働者災害補償保険法が成立した際、労働基準法の法律番号が第49号、労働者災害補償保険法の法律番号が50号というように2つの法律が、一連の流れの中で成立したことと、労働基準法における災害補償を労働者災害補償保険法という別の法律で担保していることから、労働者災害補償保険法の中に定義がなくとも、労働基準法上の労働者とされております。
労働者であることのメリット、そして忘れてはいけない…
以上、書く法律における労働者の定義を見てきたところですが、各法律(主に労働基準法になりますが)の労働者に該当することによって、当然のことながら、その法律の保護を受けることが可能となります。
一定のルールで賃金を受けることが出来る、労働時間数の上限がある、年次有給休暇を取得できる、一方的な契約の解除(解雇)にも手続き上のルールがある等、様々な法律上の保護を受けると共に、少し目線を変えれば、雇用保険、健康保険そして厚生年金保険と言った社会保険にも加入し、日々の生活上のメリットを受けているとも言えます。
これらは労働者であることによる権利と言っても良いかもしれませんが、当然、権利があれば義務もあります。以前のコラムでも記載しましたが、近時、権利ばかりに目が行ってしまい、果たすべき義務が疎かになってしまっているような事案等を見聞きします。当然、自分が働きたい環境及び労働条件は誰にでもあることかと思いますが、お互いが一定の関係性の中でWin-Winの状態にいられるようにすることの重要性が、今後、増していくのではないかと思っています。
更なる働き方の多様化に向けて
今回は、「労働者とは」という視点でコラムを書かせて頂きました。
今年度は、コロナ禍から従来の日常へ戻りつつある中で、各企業が今、そして今後の働き方に対して、試行錯誤しながら労務管理を実施してきた1年であったと思います。
また、この状況は、労働者を含め、働く人全てに対し、それぞれの働き方を見直すきっかけになったのではないかと思います。労働者不足と言っていたと思えば、大手IT企業等に見られる人員整理等、今後も企業を取り巻く環境は日々変化し続けることかと思います。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、クライアントの置かれている状況、担当者の考えや想いにしっかりと寄り添い、その状況下において企業が実施すべき対応や決定をサポートしておりますので、気になることがありましたら、お気軽にお声がけ頂きたいと思います。
松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。