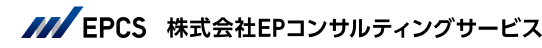コラム
請負契約と準委任契約の違い|どちらを選ぶべきか解説します

人件費の削減や業務の効率化などを理由に、アウトソーシングの利用を検討中の企業の人も多いでしょう。アウトソーシングには、大きく分けて「請負契約」と「準委任契約」があるため、それぞれの違いを理解していないとどちらが自社に向いているか判断しづらいです。
そこで今回は、請負契約と準委任契約の特徴や異なるポイント、どちらを選ぶべきかについて解説します。本記事を読めば、外部に業務を依頼したい場面で役立つので、ぜひ参考にしてください。
請負契約とは

請負契約とは、発注者が依頼した仕事を受注者が完成させることによって報酬が発生する契約形態を指します。たとえば、業者から工務店がマンションの建築を請け負った場合、建物の建築が完成すれば報酬が発生しますが、完遂できないなら債務不履行とされます。
業務を行うだけでは報酬が発生することがなく、あくまでも仕事の完遂が求められる点が特徴である契約です。
準委任契約とは
準委任契約とは、成果物ではなく、依頼された業務を行うこと自体に対して報酬が発生する契約を指します。報酬の条件として仕事の完遂は求められておらず、あくまでも委託者と受託者の信頼関係にもとづいて契約が結ばれるのが特徴です。
準委任契約は、大きく分けて「履行割合型」と「成果完成型」の2つに分類されます。それぞれどのような特徴があるのか詳しく解説します。
履行割合型
履行割合型とは、業務の遂行した割合に応じて報酬が発生する契約です。たとえば、弁護士に訴訟の代理人を依頼した場合に、履行割合型の準委任契約を結んでいれば、すべて敗訴となっても受託者は稼働した時間に応じた報酬を請求できるわけです。
また他の業種でも同様であり、委託者の望み通りの結果にならなかったとしても、実施されていれば、受託者はその時点で遂行した割合に応じて報酬を請求できるのが履行割合型の特徴です。
成果完成型

成果完成型とは、業務の遂行によって得られた成果に対して報酬が発生する契約です。たとえば、弁護士に訴訟の代理人を依頼した場合に、成果完成型の準委任契約を結んでいれば、委託者が訴訟に勝訴し利益を得れば報酬が発生しますが、敗訴となった場合には発生しません。
履行割合型とは異なり、訴訟のために労力や時間を費やしても、遂行した業務に対して報酬が発生しない点が大きな特徴の契約と言えます。
請負契約と準委任契約の違い

外部に依頼する点は共通している請負契約と準委任契約ですが、目的や義務など異なる点が多いです。どちらを利用するのが自社に最適なのかを見極めるために、請負契約と準委任契約の違いをわかりやすく解説します。
契約の目的
請負契約と準委任契約の大きな違いとして、受注者に求める目的の違いが挙げられます。
<契約の目的の違い>
- 請負契約:仕事を完遂すること
- 準委任契約:業務を実施すること
仕事の完遂を受注者に求める場合は「請負契約」が向いており、一方成果物が生じるかどうかは関係なく、業務を遂行すること自体が目的のケースでは「準委任契約」が適切だと言えるでしょう。
受注者が負う義務
請負契約と準委任契約では、受注者が負うことになる義務の重さにも違いがあります。
<受注者が負う義務の違い>
- 請負契約:完成責任、契約不適合保責任
- 準委任契約:善管注意義務
一般的に、仕事の完遂が条件とされる請負契約の方が重い義務が課せられます。なぜなら完成責任があるだけでなく、契約の内容に適合しないものがあった場合に「契約不適合保責任」を負う義務もあるためです。契約不適合保責任とは、成果物に不具合があった際に修正作業や損害賠償、契約解除を受注者に要求できる仕組みを指します。
準委任契約では、受注者が完成責任と瑕疵担保責任を負わずに済む反面、「善管注意義務」が課せられます。善管注意義務とは、最低限の注意を払って業務を行わなければならない義務を意味します。万が一、手抜き作業があると判断された場合には、たとえ準委任契約を結んでいたとしても、受託者に賠償金を請求できます。
報酬の発生時期
請負契約と準委任契約は、報酬の発生時期が異なるのも大きな特徴のひとつです。
<報酬の発生時期の違い>
- 請負契約:成果物を納品した時点
- 準委任契約:業務を遂行した時点
仕事の完遂が条件とされている請負契約では成果物を納品した時点で報酬が発生します。一方業務を行うこと自体を条件としている準委任契約では、業務を遂行し終えた時点で報酬が発生します。
契約解除の可否
請負契約と準委任契約では、契約解除ができるタイミングにも違いがあります。
<契約解除の可否の違い>
- 請負契約:仕事の完成前であれば可能
- 準委任契約:いつでも可能
どちらも契約解除自体はできますが、仕事の完遂が条件とされている請負契約の場合、完成した後では契約解除が認められていません。一方準委任契約では、委託者・受託者のどちらから申し出たとしても、タイミングを問わず契約解除できます。
ただし、請負契約・準委任契約ともに契約解除を行える場合でも、タイミングや状況によって損害賠償が発生する可能性がある点には注意が必要です。
再委託の可否
請負契約と準委任契約では、一度請け負った業務を第三者に代行してもらう再委託の可否も異なります。
<再委託の可否の違い>
- 請負契約:基本的に可
- 準委任契約:基本的に不可
仕事の完遂が条件とされている請負契約では、その業務を誰が行うかまでは指定されていないため、第三者に再委託しても問題ない場合がほとんどです。しかし、委託者と受託者の信頼関係にもとづいて契約を結んでいる準委任契約では、発注者が認めている場合や、やむを得ないケースを除いて、基本的に再委託できません。
請負契約と準委任契約のどちらを選ぶべきか?
請負契約と準委任契約の違いを理解しても、自社がどちらを利用するべきなのか、わからない人もいるでしょう。請負契約と準委任契約が適しているシーンをそれぞれご紹介しますので、実際に利用することをイメージしてください。
請負契約が適しているシーン
請負契約は、明確な成果物が求められるシーンに適しています。たとえば、システム開発などのIT系の仕事や建物の建築、運送などといった仕事の完成を求める依頼では、準委任契約よりも請負契約の方が向いていると言えるでしょう。
準委任契約が適しているシーン
準委任契約は成果物よりも、依頼した業務の遂行が求められるシーンに適しています。たとえば、家庭教師やマンションの管理、エステなどといった一定期間継続して依頼したい場合や依頼内容が明確に決まっていないケースでは、準委任契約の方が向いていると言えるでしょう。
まとめ
今回は、請負契約と準委任契約の特徴や異なるポイント、どちらを選ぶべきかについて解説しました。発注者が依頼した仕事を、受注者が完成させることによって報酬が発生する請負契約は、明確な成果物が決まっている場合に適しています。一方成果物ではなく、委任された業務を行うことに対して報酬が発生する準委任契約は、業務の遂行が目的の場合に適していると言えるでしょう。
一見似ている請負契約と準委任契約ですが、契約の目的や受注者が負う義務、報酬の発生時期など異なるポイントが多く、最適のサービスを見極めることは難しいと言えます。そこで役立つのが、「株式会社EPコンサルティングサービス」が提供するサポートサービスです。
株式会社EPコンサルティングサービスが行うプロフェッショナルアウトソーシングでは、高い専門性を持ったチームが総務・会計・経理などの管理業務を支援し、高品質かつスピーディに御社をサポートいたします。月次会計業務や決算業務、資金管理業務、労務管理業務などでアウトソーシングの利用を検討している場合は、株式会社EPコンサルティングサービスに一度お問い合わせください。