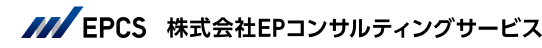コラム
年次有給休暇管理簿とは|作成義務はある?管理方法や記載すべき項目も解説!

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の取得・使用状況を把握するために雇用者が作成する帳簿です。しかし、記載が義務付けられている内容もあるため入念に作成する必要があります。そこで本記事では、年次有給休暇管理簿の作成方法や記載すべき項目について詳しく解説します。
年次有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の利用状況を管理する記録帳です。従業員が取得した有給休暇の使用履歴や残日数などを記録して、労働者と雇用者の双方が有給休暇に関する情報を確認するために作成されます。
作成義務
雇用者には、従業員へ年次有給休暇を与えた際に、時季や日数、基準日を記載した書類の作成義務が労働基準法によって課されています。
<作成義務の内容>
- 年次有給休暇の付与状況
- 年次有給休暇の利用状況の記録
- 年次有給休暇の残日数の計算と記録
作成しなかった場合でも原則罰則はありませんが、指導が入る可能性があります。そのため従業員の権利と労働法の規制についての正確な情報を確認して、適切な年次有給休暇管理簿を作成するのが良いでしょう。
保管期間
年次有給休暇管理簿における従業員の労働関連の記録は、労働基準法に基づいて3年間の保管期間が義務付けられています。なお、3年間の保管期間に違反した場合でも基本的に罰則はありません。
対象者
年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられている対象者は、年次有給休暇を10日以上付与される労働者です。対象者が限定されている理由は、労働基準法の改正によって、2019年4月からすべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられたためです。
年次有給休暇管理は正社員だけでなく、派遣労働者や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して作成しなければなりません。
年次有給休暇の管理方法は3種類

年次有給休暇の管理方法は「紙」「Excel」「管理システム」の3種類です。それぞれの管理方法におけるメリット・デメリットを解説します。
紙
年次有給休暇を紙で管理する企業もあります。年次有給休暇を紙で管理する場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
<紙で管理するメリット>
- コストを抑えられる
- シンプルでわかりやすい
- 自由にカスタマイズできる
<紙で管理するデメリット>
- 数値の計算ミスや誤記載のリスクがある
- 情報を探しづらい
- 保管スペースが必要になる
- セキュリティ面に不安がある
紙で行われる年次有給休暇の管理には、コストカットや手軽さ、柔軟性といったメリットがある反面、ヒューマンエラーや情報を探す手間、データセキュリティの懸念などのデメリットもあります。そのため組織の規模やニーズ、セキュリティ要件に応じて、紙での管理かデジタル化かを慎重に検討することが大切です。
Excel
企業によっては年次有給休暇を使い慣れているExcelで一括管理したいと考えているケースも多いでしょう。年次有給休暇をExcelで管理するメリットとデメリットは、以下のとおりです。
<Excelで管理するメリット>
- データを自動計算できる
- 情報の検索や集計が簡単
- データのバックアップができる
- セキュリティ対策がとれる
- テンプレートやフォーマットを自由にカスタマイズできる
<Excelで管理するデメリット>
- 数値の誤入力などのリスクがある
- パスワードの漏洩や不正アクセスのリスクがある
- データの増加や複雑な検索や集計に対応しづらい
- データを共有する際にバージョン違いで混乱が生じるリスクがある
Excelを利用すれば、従業員の年次有給休暇を効率的に管理できます。データの入力・更新が容易なため、計算機能や集計機能を活用して必要な情報を簡単に取得できるのも魅力です。
またExcelの柔軟性を活かしてテンプレートをカスタマイズすれば、最適な管理方法を模索しやすい特徴もあります。しかし、Excelで管理する際はデータの整合性や正確性の確保、セキュリティのリスクなどのデメリットもあります。
なお、厚生労働省のホームページでは「年次有給休暇管理簿」のテンプレートをExcel形式で提供しています。テンプレートには、従業員の基本情報や年次有給休暇の付与・利用状況を入力する欄が設けられており、自動計算機能や合計表示などが組み込まれていますので、使ってみてはいかがでしょうか。また自社の要件に適合させるようにカスタマイズする方法もおすすめです。
管理システム
資金に余裕がある場合は、年次有給休暇の管理システムを導入する方法も良いでしょう。年次有給休暇を管理システムで管理するメリットとデメリットは、以下のとおりです。
<管理システムで管理するメリット>
- 管理業務を自動化できる
- 正確に管理できる
- カスタマイズ性が高く管理しやすい
- 複数人で同時にアクセスできる
- レポートや分析の機能がある
- 情報漏洩やデータ損失のリスクが低い
<管理システムで管理するデメリット>
- 導入コストがかかる
- 学習コストがかかる
- システムアップデートなどの維持コストがかかる
管理システムを導入すれば、管理業務を自動化できたりデータの計算ミスを防げたりするため、効率的で正確な年次有給休暇の管理を実現できます。またカスタマイズ性が高く、付与条件や計算方法、休暇申請のルールなどを柔軟に設定することも可能です。
ほかにも複数のユーザーが同時にアクセスし、リアルタイムで情報を共有できたり、レポートや分析を行う機能を搭載していたりするなど魅力的なポイントが多いです。管理システムには、アクセス制御やバックアップなどの機能も備わっているため、情報漏洩やデータ損失のリスクを軽減する効果も期待できます。
ただし、初期費用やライセンス料、システムアップデートの維持のために費用がかさみがちな点には注意が必要です。またシステムの操作方法や設定に関する研修が必要な場合が多く、学習時間のコストがかかる点も無視できないでしょう。
年次有給休暇管理簿の記載項目
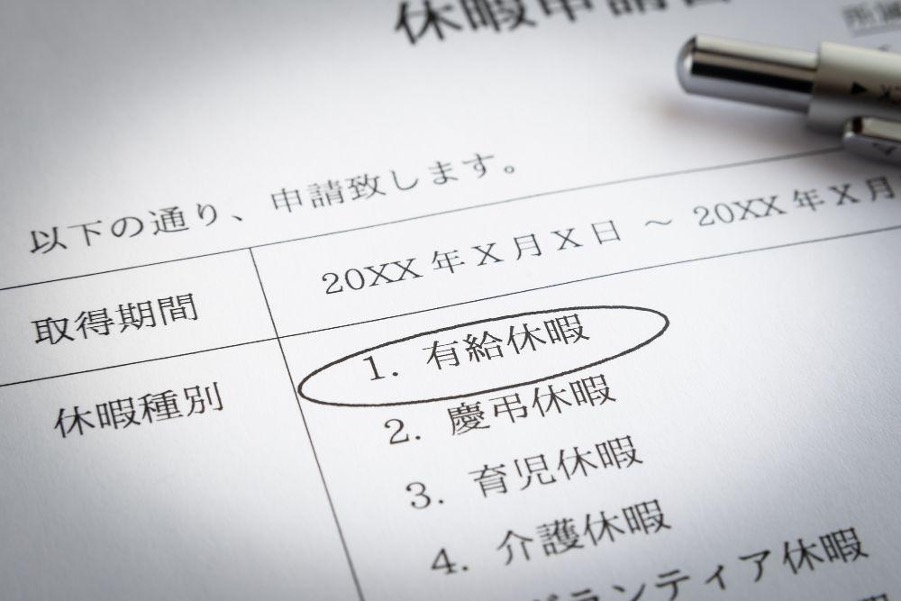
年次有給休暇管理簿を作成する際には、ポイントとなる記載項目が存在します。特に記載が義務付けられている項目を3つご紹介します。
時季
年次有給休暇管理簿には、必ず「時季」を記載しなければなりません。時季とは、従業員が年次有給休暇を取得した日のことです。たとえば、2023年8月2日に年次有給休暇を取得した場合は、「2023年8月2日」と記載する必要があります。
時季を記載しておけば、従業員の年次有給休暇の取得期間や有効期限を把握しやすくなる効果が期待できます。また企業や業界によっては、季節に応じた休暇の利用促進やバランスの調整を行うために時季を記載する場合もあります。
日数
従業員の有給休暇に関連する「日数」も記載しなければなりません。日数とは、基準日から1年間で従業員が利用した有給休暇の使用日数や有給休暇の残日数を意味します。
<記載する日数の項目>
- 使用日数:従業員が年次有給休暇を実際に利用した日数
- 残日数:従業員がまだ使用していない有給休暇の残りの日数
基準日が2つ存在する場合は、1年ごとの取得日数を記載しておけば、年5日の取得義務を果たしているかを一目で確認できます。日数情報は監査でチェックされますので、必ず記載しておきましょう。
基準日
年次有給休暇管理簿に記載する「基準日」とは、有給休暇を付与した日付です。企業では基準日から1年間で5日の有給休暇の取得が義務付けられているため、必ず記載しておかなければなりません。
まとめ
本記事では、年次有給休暇管理簿の管理方法や記載項目について解説しました。年次有給休暇管理簿は、従業員の年次有給休暇の利用状況を管理するために重要な記録帳です。
年次有給休暇の管理方法には紙・Excel・管理システムの3種類がありますが、どれも費用や手間がかかるため、管理業務を負担に感じる企業も多いでしょう。そこで年次有給休暇の管理でお困りの際には、「株式会社EPコンサルティングサービス」の利用をおすすめします。
株式会社EPコンサルティングサービスが提供するプロフェッショナルアウトソーシングサービスは、年次有給休暇管理簿の作成・管理など企業の運営に深く関わる業務を丁寧にサポートします。また総務・経理などの管理業務やコア業務への経営資源集中にも貢献します。
御社の業務を総合的にサポートしますので、人手不足などでお困りの際には株式会社EPコンサルティングサービスに一度お問い合わせください!