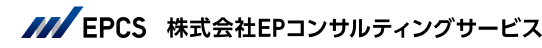コラム
決算整理とは|目的や実際の手順をわかりやすく解説します!
決算時には、期中に作成した帳簿とズレが生じないよう、決算整理仕訳を行う必要があります。しかし、決算をはじめて迎える企業の人や経理業務に不慣れな場合は、どのように行えばよいかわからないケースも多いでしょう。そこで本記事では、決算整理の概要や目的、実際の手順をわかりやすく解説します。
決算整理仕訳とは?

決算整理仕訳とは、損益計算書や貸借対照表をより正確に作成するために、期中の仕訳と決算時の情報とのズレを調整する仕訳作業です。企業の経理作業は、基本的に期中の取引を仕訳帳に記載するだけで完結します。しかし決算の際には、期中に作成した仕訳帳と決算時の情報を照らし合わせ、ズレが生じている場合には調整するための決算整理仕訳を行わなければなりません。
決算整理仕訳は、取引数が多い企業では期末に多くの調整が必要になるため、相当の手間とコストがかかります。
決算整理仕訳の目的
なぜ決算整理仕訳を起こす必要があるかというと、企業では期中の仕訳と決算時点の情報にズレが生じるケースが少なくないからです。たとえば取引が事業年度をまたぐ場合には、今期の売上でも取引先からの入金は来期になるケースがあると、期中の仕訳帳と決算時の金額にズレが発生します。
このようなズレを調整し、数値上の矛盾をなくす点が決算整理仕訳の目的です。損益計算書や貸借対照表などの財務諸表の作成に用いる数字の確実性を高めるために、決算整理仕訳が行われるのです。
決算整理仕訳の手順

決算整理仕訳の手順をわかりやすく解説します。
①売上が漏れなく計上されているか確認
まずは「発生主義」にのっとって、売上が漏れなく正確に計上されているかを確認します。
<発生主義・現金主義・実現主義の違い>
- 発生主義:取引が発生した時点で費用と収益を帳簿に計上する
- 現金主義:実際に入金や出金が行われた日に帳簿に計上する
- 実現主義:実際に収益を得る権利が確定した時点で帳簿に計上する
日本企業の会計基準では、費用は「発生主義」、収益は「実現主義」で計上することが原則とされています。つまり、売上は入金日ではなく、商品を納入した納品日に計上しなければなりません。
一例として、3月決算の企業で2月に受注した商品を3月に納品し、入金が4月にずれ込んだ場合の計上のタイミングを見ていきましょう。
<会計基準別の売上計上のタイミング>
- 発生主義:納品した3月に売上を計上する
- 現金主義:入金される4月に売上を計上する
掛取引や信用取引が一般化している昨今では、来期ではなく今期に売上を計上できる発生主義の考え方を採用したほうが便利です。決算整理仕訳を起こす際は、当期に納品された金額がすべて今期の売上に正しく計上されているか必ず確認しておきましょう。
②現金に過不足があるかチェックする
決算整理仕訳では、現金に過不足がないか、実際の残高が帳簿の残高と一致するかをチェックする点も重要です。
<不一致の場合に考えられる原因>
- 利息などの計上ミス
- 相手先が換金していない未取付小切手がある
- 銀行の都合で換金ができていない未取立小切手がある
どうしても原因がわからない少額の誤差が生じた場合は、雑損失・雑収入で処理することも認められています。また決算整理仕訳の手間を省くためには、現金に過不足が出ないように普段から残高確認を徹底しておくことが大切です。
③銀行残高の過不足も確認する

決算整理仕訳では、現金だけでなく、銀行残高の過不足も確認する必要があります。銀行の残高証明書または決算日の通帳残高と、預金勘定の残高を照らし合わせて一致しているか確認しましょう。銀行残高も過不足が出ないように、現金と同じく普段から確認しておくことが重要です。
④当期費用の漏れがないか確認する
決算整理仕訳では、未処理の当期費用がないか、来期の費用が含まれていないかを把握する点も重要です。たとえば当期に支払った保険料が来期のものだった場合、前払費用として計上するなど、適切な決算整理仕訳を行う必要があります。
毎年度正確に決算を行うためには、どの費用を前払費用や未払費用として計上するのか、判断基準を明確にしておきましょう。また今期の費用をその期中に正しく計上できるように、仕訳漏れがないか確認しましょう。
⑤棚卸資産を確認して売上原価を求める
棚卸資産は売れた時点で費用になるため、決算整理の際に数量や状態を確認し、在庫分を差し引いて、実際に販売した商品の「売上原価」を求める必要があります。
<売上原価の計算式>
- 売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高
売上原価とは、売上高を生み出すために商品を仕入れたり製造したりすることで発生する費用を指します。決算時には、仕入金額の全額がそのまま費用として計上されるわけではありません。実際に販売した商品の売上原価が、費用として計上されるため必ず計算しておきましょう。
⑥減価償却費を計上する
決算整理仕訳では、固定資産の減価償却額の正確性を確認したうえで減価償却費を計上します。減価償却とは、固定資産の取得にかかる費用を耐用年数に応じて配分して計上していく処理方法です。
減価償却額が正しいかどうかは、12ヶ月分の合計償却額が固定資産台帳に記載された金額と一致しているかを確認して判断します。間違いがないことを確認できたら、減価償却費を計上しましょう。なお会計ソフトを利用している場合は、固定資産台帳システムに資産の種類や取得価格、耐用年数等を入力すれば、自動仕訳機能により月次更新するだけで償却処理できます。
⑦有価証券の評価替えを行う
売買目的の有価証券を保有している場合は、期末時価を確認して評価替えも忘れないようにしましょう。有価証券の評価替えとは、取得時の帳簿価額と決算時の時価に差額がある際に、評価損益として調整する処理方法です。売買目的の有価証券では、時価を貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する必要があります。
⑧未収入金を確認する
期中取引で有価証券や建物などの資産の売却を行った場合は、未収入金を確認することも重要です。未収入金とは、営業取引以外の取引で発生する将来現預金のうち回収が見込まれる収入を指します。
<未収入金の例>
- 建物や機械、車両の売却額
- 有価証券の売却額
- 家賃収入
未収入金として計上するには、決算後1年以内に回収予定の営業活動以外で発生した収益でなければなりません。また売掛金を間違って未収金として計上してしまうと、不正会計を疑われる可能性があるため、決算書で明確に分けておかなければならない点にも注意が必要です。
なお上記の例以外にも、中間納付がある消費税や概算納付している労働保険料も未収入金として計上するケースがあります。
⑨各種引当金を計上する
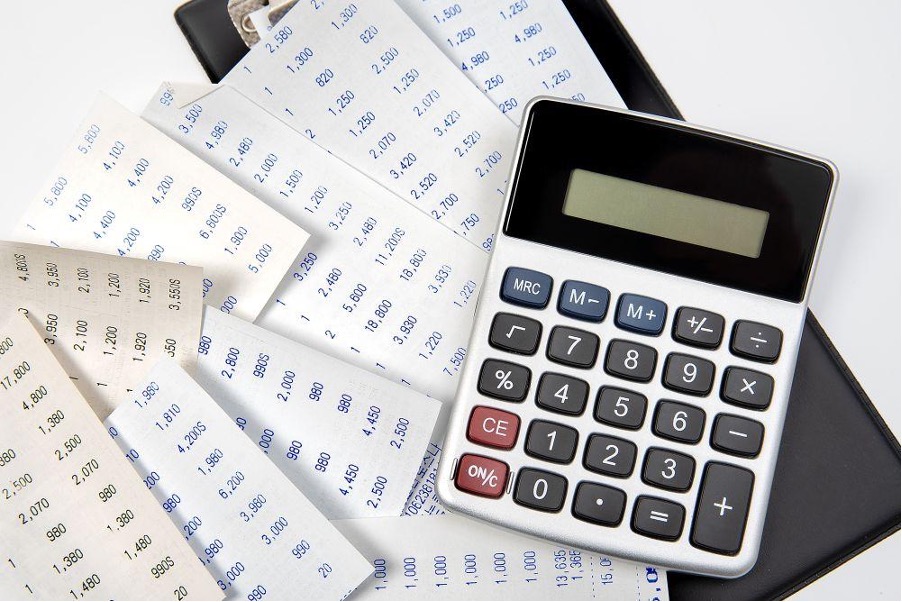
貸倒れのリスクや従業員の退職予定などがある場合は、各種引当金を計上しましょう。引当金とは、将来発生するリスクがある費用や損失に対する準備として、当期の費用に組み込む見積もり額を指します。
<各種引当金の例>
- 貸倒引当金:売掛金や受取手形などの貸倒れ見込み額を計上する勘定科目
- 賞与引当金:来期に従業員へ支払う賞与を事前に計上しておく勘定科目
- 退職給付引当金:従業員の将来の退職金を事前に見積もり計上しておく勘定科目
引当金は見積もり額なので、計上額どおりにならなかったとしても問題ありません。引当金で事前に見積もって準備しておけば、期間損益を正しく計算できるだけでなく、投資家などの利害関係者により正確な財務諸表を提示できます。
まとめ
本記事では、決算整理仕訳を行う概要や目的、実際の手順について解説しました。期中に起こした仕訳と決算時の情報では、ズレが発生するケースは珍しくないため、正確な損益計算書や貸借対照表を作成するには、決算整理仕訳が欠かせません。ただし、決算整理仕訳を行う際は、現金・預金の過不足チェックや当期費用や未収入金の確認、減価償却費の計上などの複雑な作業が多く、経理担当者の大幅な負担につながってしまいます。
決算時の負担を減らしたい場合や決算整理仕訳が難しく感じる場合は、「株式会社EPコンサルティングサービス」の利用を検討してください。株式会社EPコンサルティングサービスが提供するプロフェッショナルアウトソーシングサービスでは、決算整理仕訳など専門性が高い複雑な業務でも対応いたします。また日常会計業務や税務業務なども幅広く対応しますので、大幅な効率化が見込めます。
決算整理仕訳の処理が不安な場合や経理業務の手間を少しでも削減したいならば、ぜひ株式会社EPコンサルティングサービスに一度お問い合わせください!